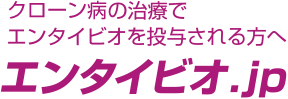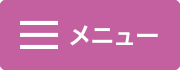監修:滋賀医科大学 消化器内科教授 安藤 朗 先生
難病医療費助成制度に
ついて
治療にお金がかかりそうで不安です…
クローン病の治療費は高額になることがあるため、法制度が整備されています。詳細は主治医や病院のソーシャルワーカーにご相談ください。
クローン病患者さんが利用できる主な法制度


難病情報センター(https://www.nanbyou.or.jp/)(2025年5月アクセス)
東京都福祉保健局 東京都心身障害者福祉センター(https://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/shinshou_techou/techonituite.html)(2025年5月アクセス)
日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html)(2025年5月アクセス)
全国健康保険協会(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/)(2025年5月アクセス)
指定難病ってなに?
厚生労働省に指定された病気で、以下の条件をすべて満たす病気を指定難病と呼びます。
- 1)発病の機構が明らかでない
- 2)治療方法が確立していない
- 3)希少な疾患
- 4)長期の療養を必要とする
- 5)患者数が日本で一定の人数(人口の約0.1%程度)に達していない
- 6)客観的な診断基準(またはそれに準ずるもの)が成立している
2025年4月現在、指定難病の数は348で、この中にクローン病も含まれています。


難病情報センター(https://www.nanbyou.or.jp/)(2025年5月アクセス)
医療費助成制度はどうやって
申請したらいいの?
指定難病の医療費助成を受けるためには、医療受給者証が必要になります。対象の病気(例: クローン病)と診断されたら、診断書と必要書類を合わせて、都道府県窓口へ申請してください。
ただし、特定の道府県については指定都市への申請になります。詳細は、都道府県・指定都市の窓口または保健所までお問い合わせください。
都道府県に申請・認定されると医療受給者証が交付されます。
指定医療機関で医療受給者証を提示すると医療費の助成を受けることができます。
申請の流れ


- 医療受給者証の有効期限は?
-
原則として申請日から1年以内で都道府県が定める期間です。1年ごとに更新の申請が必要です。
※難病指定医を受診し、診断書の交付を受ける。難病指定医及び指定医療機関については、難病情報センター
ホームページで検索するか、お住まいの都道府県の窓口にお問い合わせください。
難病情報センター(https://www.nanbyou.or.jp/)(2025年5月アクセス)
医療費助成制度を使うと自己負担額はどれくらいになるの?
日本の医療費自己負担割合は多くの方が3割ですが、指定難病患者さんへの医療費助成制度を利用すると2割に軽減されます。
さらに自己負担額に上限が定められており、2割の金額と上限額のいずれか金額の低い方が自己負担額となります。
※自己負担額の上限は世帯の所得により変わります
<注意>
医療費助成の対象となるのは、原則として指定難病と診断され、重症度が一定程度以上の患者さんです。ただし、軽症の患者さんでも医療費総額が33,330円を超える月が過去1年以内に3回以上ある場合*は医療費助成の対象となります。
*例:医療保険3割負担の場合、医療費の自己負担額が約1万円となる月が年3回以上ある患者さん
医療費助成における自己負担額の上限(月額)


※「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある者(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上)。
厚生労働省 難病の方へ向けた医療費助成制度について
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nanbyou/)(2025年5月アクセス)
難病情報センター(https://www.nanbyou.or.jp/)(2025年5月アクセス)
医療費助成 ワンポイントコラム

助成の開始時期が、申請日から「重症度分類を満たしていることを診断した日」へ
これまで、医療費助成の支給対象期間は、医療受給者証の交付の申請日以降に指定医療機関で診療等にかかった医療費でしたが、改正後は「重症度分類を満たしていることを診断した日※1」から助成の支給対象期間となります。
ただし、医療受給者証の交付の申請日以前のさかのぼり期間は原則1ヶ月となりますので、診断日から1ヶ月以内に申請を行う必要があります。
指定医が診断書の作成に期間を要した場合や入院、その他緊急の治療が必要であった場合など、やむを得ない理由※2で申請が遅れた場合は、申請日から最長3ヶ月までさかのぼることができます。

- ※1
軽症の患者さんでも「⾼額な医療を継続することが必要」な場合には対象となります。
「⾼額な医療を継続することが必要」とは、⽉ごとの医療費総額が33,330円を超える⽉が年間3回以上ある場合(例えば医療保険の3割負担の場合、医療費の⾃⼰負担が1万円以上の⽉が年間3回以上)です。 - ※2
「臨床調査個⼈票(診断書)」の受領に時間を要した、診断後すぐに入院することになった、大規模災害に被災したなど
- ※3
2023(令和5)年10月1日以降の申請から適用となります。2023年10月1日より前の医療費については助成の対象とはなりません。
- ※4
特定医療費の支給開始日を確認するため、「臨床調査個⼈票(診断書)」に新たに「診断年月日」の欄が設けられ、難病指定医が「臨床調査個⼈票(診断書)」に診断した日を記載します。
難病情報センター(https://www.nanbyou.or.jp/)(2025年7月アクセス)
【動画】知っていますか?指定難病の医療費助成制度
【監修】医療法人社団晃輝会 大堀IBDクリニック 院長
東京医科大学病院 消化器内科 兼任教授
吉村直樹 先生
潰瘍性大腸炎やクローン病など指定難病の患者さんは医療費助成を受けられる可能性があります。
どのような方がどのような助成を受けられるのでしょうか。
こちらの動画で医療費助成制度についてご説明しています。